佐藤優さんの読書術の本を読んだら、速読には理解力を高めないといけないから高校の勉強で苦手なところを復習するといいと書いてありました。
高校の科目の中でも全体の基本になっているのが国語で、特に現代文がすべての学問の理解や学習の基礎になっています。
国語が基本だというのは当たり前といえば当たり前の話ですが、国語力は自分で意図的に高めることが出来ます。
盲点でしたが自分の力で自分の頭をよくすることが出来るということです。
学ぼうとしない人は成長も成功もしない
YouTubeで「バカは自信過剰」と言ってる人がいました。
自信満々なので学ぶ必要がないと考えているので成長しないし、人の話もちゃんと理解できないので人からも好かれません。

自分が言ってることもこっちの話のリアクションもズレてる人っているでしょ。
あれは言葉を正確に理解する力が弱いのが原因なんだ。
国語力の弱い人は言ってる話に矛盾が多く、そもそも自分の気持ちもちゃんと理解できていません。
人の気持ちも自分の気持ちも言語化しないと理解できないのですが、この言語化や言語化に必要な客観的で正しい分析ができないからです。
自信過剰の逆で自信不足の人の中にも頭の悪い人はいます。こちらは頭が悪いと自分で決めつけて学ぼうとしないので頭がよくなりません。
ですが、自信が過剰でも不足していても国語(言葉)のルールさえ理解してしまえば国語力は高められるので大丈夫です。
国語力がないと自分のことも相手のことも、また仕事の話も正しく理解できず、人間的にもビジネス的にも成長できません。
早めに高めておいたほうがメリットが大きくなるので、自分の頭をもっとよくしたい人は先に学んでおくといいです。
学ぶべき3つのこと
- 正確な理解方法 ⇒ 正しい人や仕事のできる人へ!
- 相手の気持ちや感じ方 ⇒ 好かれる人になれる!
- 伝え方 ⇒ 仕事や恋愛など人間関係がうまくいく!
大人が国語力を上げる目的を単純化すると、頭を良くしたいか、うまく話せるようになりたいとまとめることができるでしょう。
その先にある本当の目的(潜在ニーズ)が、ここに挙げた3つに含まれているはずです。
正確な理解方法
これがこの記事のメインテーマです。
言葉を正確に理解することが基本なので、まずはここに力を入れてください。
これだけで正しい判断ができるようになっていきます。
仕事の精度も上がり、仕事ができる人だと周りから評価されるようになっていくはずです。
相手の気持ちや感じ方
気持ちや感じ方を理解するうえで前提になるのは、人は自分のことすら正しく理解できなかったり、意図的に嘘をつくことがあるという事実です。
言葉や反応のすべてが正しいものとは限りません。
間違っている可能性があれば、後から変わることもあるので注意してください。
自分で自分の気持ちを誤解していることもあるので、人の心は難しいです。
また残念なことですが、政府やマスコミが悪質な印象操作を続けていることがあります。
さらに、それを悪用して意図的に人をだます詐欺師やカルトネットワークまであります。
それらにも注意が必要ですが、正しく学んでいけば、嘘を見破れるようになるので頑張ってください。
それでは本題に入ります。
心理学や脳科学などで研究されているように、人の気持ちや感じ方には一定のルールがあります。
一言で人間関係を破滅的に破壊してしまうことがあります。
相手が大切にしている信念を、結果的に否定してしまうときは特に危ないです。
否定や批判は、自分が思っている以上に相手にダメージを与えてしまう恐れがあります。

自分が好きな人をバカにされたらイヤでしょ?
強い否定や批判はそれくらい強力なの。
相手がどんな人かわかるまでは、否定も批判もしないほうが無難です。
せっかく正確な分析ができるようになっても、立場や関係性によっては、正しいことでも言ってはいけないことがあります。
いくら正しくても、相手にとって不都合な真実であった場合、相手を強く傷つけ、その結果、不要な恨みを買うおそれがあります。
正しいことは否定できない厳しい事実として、その人を傷つけ続けてしまうかもしれません。

かなわない夢を追っている人に「絶対ムリだ」なんていったら一生恨まれるぞ!
夢を追うのは自由だから、かなわないということは自分で理解してもらうべきなんだ。
変な夢を終わらせたいなら、どうやって、いつごろ実現できそうか聞いてみたりして、現実に目を向けてもらうほうがいいな。
また、人の気持ちや感じ方は、その人の知識や常識感覚などへの信念によってまったく違うものになることがあります。
たとえば、恋する二人の目には相手が素敵な人だと映っていることでしょうが、周りから見たら残念なバカップルに見えたりするのがいい例です。
さらに、信念を作り上げる認識自体も間違っていることがかなりあります。(詳しくは「認知バイアス」で検索を)
これらのことから、人の気持ちや感じ方を理解するには、関係性や認知バイアスなどを理解しておいたほうがいいです。
相手を理解するのは難しいことですが、理解していくにつれて好かれる人になっていけるので、努力すべきでしょう。
これはこの記事では説明していませんので、心理や人間関係、認知バイアスなどを各自で学んでみてください。
私が意外とおすすめなのは恋愛や結婚の心理分析です。
恋愛や結婚ほど相手のことを深く分析しようとすることはないので、深い分析を学べます。
次の『愛とためらいの哲学』という本は、私が思った以上に勉強になったと感じた本です。
最初は、興味はないが一応読んでみようと思っただけなのですが、予想以上の良書でした。
理論的な部分はあまり納得できない部分もありました。本の内容にすべて従うべきだとも思いません。
ですが、4章の幸福になるための「愛する技術」では、私が気付いていなかったいろいろな心模様を学ぶことができました。
私は恋愛本に詳しくないので、もっといい本があるかもしれませんが、4章だけは読んでおくことをおすすめします。
普段は気付けないいろいろなとらえ方を学ぶことができるはずです。
私が読んだときは Kindle Unlimited の月額980円の読み放題にラインナップされていたので安く読めました。
Kindle Unlimited は期間限定で良書もタダになり、本をダウンロードして保存しておくこともできるので、思ったよりもお得感がありました。
【PR】Kindle Unlimited ガイド伝え方
ひとつ前の項目で紹介した『愛とためらいの哲学』でも説明されていますが、伝え方が一番難しいです。
立場や相手との関係性で、言葉の意味合いが変わってしまうからです。
どうしたらうまく伝えられるのかというと、まずは相手と良好な関係を築くことが大切です。
人は嫌いな話は聞かないからです。すでに嫌われてしまった相手に、何かを正しく伝えることはかなり難しいです。

キャバクラのママが若い子に指導するときは、まずはほめまくって仲良くならないとダメだっていう話を聞いたわ。
女社会はそれくらい嫌われるとダメだってことね。
仲良くなったら、次は相手のことにちゃんと興味を持って、相手を理解することが大切です。
人は無意識に対等な関係を求めるので、自分に興味のない相手には興味を持ちにくいです。
そのような努力をへて、やっと相手のことが分かり、相手も話を聞く準備ができあがります。
ここまでくれば、あなたのお願いやアドバイスなどが、相手に受け入れられるはずです。
ところが、いい考えでも、いうことをすぐに聞いてくれるとは限りません。
人はそう簡単には考えを変えませんし、他人の指図を受けることを嫌います。
ですが、自分の考えが伝わり、それがいい考えだと相手が理解してくれれば、まずは成功といえます。
相手の頭のなかにその考えが入っていれば、何かのきっかけでいつかその考えを相手が実行してくれる可能性があります。
この伝え方についても、この記事では扱っていないので、前の項目「相手の気持ちや感じ方」と同じように、検索や本などで学んでください。
伝え方は仕事と恋愛とではかなり違うので、目的に応じて学んだほうがいいです。
基本的には文章か会話で伝えるので、次の本がおすすめです。
ここまで学べれば、仕事や恋愛など人間関係はどんどんいい方向に向かっていくはずです。
うまくいかないとすれば、何か問題があるはずなので、もう一度学び直してみてください。
例外的に正しいことをそのまま伝えても問題のないタイプの人もいます。
それは科学者などの客観的な事実を客観的に理解できるタイプの人です。
論理的思考力が高く物事を冷静にとらえることができる相手なら、腹を立てずに話を聞いてくれる可能性が高いです。
とはいえ、彼らにも価値観や信念上、受け入れがたいことはあります。
何を言ってもいいという訳ではないので注意してください。
まとめとさらなるメリット
- 正確な理解方法 ⇒ 正しい人や仕事のできる人へ!
- 相手の気持ちや感じ方 ⇒ 好かれる人になれる!
- 伝え方 ⇒ 仕事や恋愛など人間関係がうまくいく!
せっかく学ぶならこの3つを意識することで、効率的に学んだほうがいいです。
特にゴールを意識して、道のりを具体的に考えておくと効率が上がります。
これらを学んでいくとさらに良いことがあります。
それは、人の文章や話から、その人が何をしようとしているかわかるようになることです。
簡単なところでは、ほめているなら仲良くなりたい、けなしているなら相手をおとしめたいのだろうと予想できます。
これを厳密に覚えていくだけでも、その人の人間関係や利害関係者がみえてきます。
良い人なら仲良くなり、悪い人なら距離をとるなど、分析の結果は次の行動をよりよいものに変えていきます。
また同じ言葉でも状況やタイミングで変わってくるので、相手の考え方や価値観などの信念を分析し続けることが大切です。
深く分析できるようになれば、よりよい人間関係を作れるようになり、嘘を見抜くこともできるようになっていきます。
これが国語力や人間観察力を高め、適切な伝え方を学ぶ最大のメリットといえるでしょう。
国語という言葉は人が使うものなので、最後は人を理解する力が重要になります。

言語学習のゴールは人間愛なんだ。

じゃあ、国語の点が低いあたしは愛がないってこと?

それは頭が悪いのが原因だから愛は関係ないよ。

もう、うるさいわねぇ。
あんたみたいなのが愛を語っていいのかねぇ。

いやいや、国語力を高めれば頭が良くなって、仕事や人間関係もうまくいくから、学んだほうがいいってことだよ。

でも、あんたもまだ学べてないみたいね(笑

学ぶ必要性が伝われば、今の話は成功だよ(笑
本を読むだけで頭がよくなる?
読まないよりもずっといいですが、先に読解力を中級以上に高めておかないと頭を良くする効率が悪いです。
本を読むだけで頭をよくするには正確に読み解く読解力が必要です。
これがない人が本を読んでも雑学の知識を増やしているだけで知識を役立てる力があまり高まりません。
言葉の意味が分からなかったり、助詞などをあいまいに理解していると内容を正確に理解できません。
まずは文章を1文字1文字まで正確に理解するスキルが必要です。
そのうえで知識を自分の中に、体系的に積みあがっていかないと頭はよくなりません。
特に国語が得意でもないのに斜め読みしてるような人は要注意です。
内容がちゃんと頭に入っているか思い出してみてください。
例えば辞書を斜め読みしてもほとんど頭に残らないはずです。
斜め読みでは自分が詳しい分野でないと内容をほとんど理解できないからです。
それよりも自分が理解できる速さで正確に読み解くことが大切です。
国語というのは意味とルールのあるゲームのようなものです。
いかに正確に意味とルール(文法)を正確に理解できるかがカギです。
運よくこの記事にたどり着いたみなさんは、良い機会なので国語の基礎を確認して頭をよくしてみてください。
今さらそんな必要ないと思うかもしれませんが、得られる学びは多いはずです。
斜め読みはダメなの?
本でもブログでも同じジャンルのものを読み続けているとすでに知っているテーマが出てきます。
知っているテーマの話は最後まで読まなくても流れや結論がだいたい同じなことが多いです。
ですから、知ってる話を何度も読んでも意味はないので読み飛ばしてもいいです。
(※これはビジネス書などの学習本の話、小説や漫画などの娯楽作品ならあきるまで何度読んでもいい)
むしろ、時間を節約できるので知ってる話は読まないほうが効率がいいです。
ということで、斜め読みは最初に読むか読まないか決めるのに役立ちます。
他にはネット掲示板などの内容が薄いものは斜め読みで十分です。
自分の頭はよくしておいたほうがお得

ぼくは頭が悪いからムリだよ

残念だけど大人になるともう頭はよくならないのよ
あきらめるのはまだ早いです。
地頭のよさは変わらないとしても、国語力なら技術的に高めていくことは出来ます。
いわゆる普通の頭のよさは基本的には理解力のことなので国語力に依存しています。
国語力を高めれば地頭はともかく一般的な頭のよさは高めていくことができます。

国語力を上げるだけで頭がよくなるなら出来る範囲でもいいので頭をよくしたい!

もっと頭がよくないと困るからなんとかしたい!
先に断っておくと、もともと国語の勉強が得意で既に限界近くまで国語力を高めてしまった人には効果が薄いです。
ですが、それ以外の人ならまだ国語力を高めることで頭をよくできるチャンスがあります。
日本人なら日本語の文法はだいたい理解しているはずです。
ですから、後は語彙力や知識量を増やし、話の流れをつかむ理解力や読解力を高めていけば国語力を高めていくことが出来ます。
理解力が高まれば分析力も高まっていき、分析力が高まれば推理力も高まっていき、推理力が高まっていけば発想力(応用力)が高まりアイディアも浮かびやすくなります。
- 理解力アップ
- 分析力アップ
- 推理力アップ
- 発想力(応用力)アップ
- 頭がいい人の仲間入り!
このように国語力を高めていけば、総合的な知的能力を高めていくことが出来るのです。
しかも国語力を高める方法は受験勉強の方法などからもう分かっています。
せっかく頭をよくする方法が分かっているのだから利用しない手はありません。
自分が出来る範囲で十分なので国語力を高めて意識的に頭をよくしておいたほうが残りの人生もよりよいものにできるはずです。
むしろ頭をよくしないでおくのは損なことなのではないでしょうか?
一般的な国語の勉強法
学生や受験生向けのイメージがありますが、いったん普通のやり方を説明しておきます。
大人なら基本は出来ているはずなので自分が苦手な部分を強化して平均点を上げる戦略がおすすめです。
漢字だけ大量に知っているだけの人よりも平均的な国語力が高い方が賢く、周りからの評価も上がりやすいからです。
- 言葉と漢字:読み書きと意味
- 文法:簡単な入門書から確実に理解
- 読解力(説明文):説明の意図や流れを読み取る
- 読解力(小説):作者の心情を見よ取る
- 作文/論文:読者に伝わる適切な表現力を高める
- 会話力:会話で情報や感情を適切に伝えたり理解する
日本の国語教育ではなぜか会話とか議論の仕方を教えていませんが、英会話学習が人気のように話す力・聞く力は大切な国語力のひとつなので追加しておきました。
会話でも文章の読解のように説明内容や相手の心情を理解することが大切です。

読解力を高めていけば自然とそうなるんだけど、自分のことより相手の言いたいことをちゃんと理解するのが大人の会話ね。
国語力を高める=頭をよくする学習法
国語力(頭のよさ)の基本は知識量の多さです。
国語力としてはまずは多くの言葉を理解して使いこなす語彙力を高めましょう。
次は言葉の表す対象や範囲、日本語の文法の意味を正しく理解して読み解く力をつけましょう。
日本語は文末になるまで肯定か否定かわからないので、最後までちゃんと理解すること、さらに接続詞や助詞なども厳密に理解することも大切です。
最後に理解したものを的確に相手に伝える力を身に着ければひとまず完了です。
後は自分の仕事や興味のある特定分野の知識を重点的に増やしていくだけです。
いくら頭がよくなっても知らないことは知らないので最後は知識の量がものを言います。
- 語彙力を高める
- 読解力を高める
- 表現力を高める
- 専門知識を増やす
語彙力を高める
語彙力とは言葉をどれだけ知っているかという能力のことなので基本は知らない言葉があったときに調べることで高めていきます。
国語力を高めるには大学受験の参考書がちょうどいいのでこれを使います。
受験業界的にメジャーな入門書が「ことばはちからダ!」という本です。
受験によく出てくる評論文で使われる言葉を中心に説明されている良書です。
語彙力アップの入門書としては、確固たる地位を築いていて、中堅大学から難関大学を目指す受験生まで幅広く推薦されている入門本です。

思ったより難しいなぁ
少し難しく感じたときは中学生向けの語彙力本にサラッと目を通しておくと理解しやすくなります。
『ことばはちからダ!』の書評(ブックレビュー)
受験生向けの入門書だけあって親切に説明された本でした。
たとえば、「具体的」や「抽象的」という言葉は普通に使っている人も多いかもしれませんが、自分で辞書を引いたのは遠い過去のことだろうと思います。
そういう言葉のちゃんとした意味を改めて確認できて面白かったです。
普通の言葉もけっこう説明されていました。
この本に載っている言葉を受験生に教えているということは偏差値50以下くらいの人たちはけっこう知らない言葉である可能性があります。
ですから勉強が苦手で全然やってこなかった人たちに「抽象的な考え方をしたほうがいい」と言ってみても意味が通じていない可能性があることに気付かされました。
本の内容は受験用なのでミニテストもあって考えさせられるところも少しありました。
とはいえ、問題はかなり少なく、ほとんどは言葉の説明や受験生向けの表論文などで構成されていました。
一応は大卒でいい歳の大人である私が読んでも知らない言葉もあったので普通に読んで勉強になった一冊でした。
私も少し頭がよくなったと実感できました。
言葉を正確に使わないといけないと気付かされる良書と言えます。
もちろん受験的な出題傾向なども分かります。できれば、受験生のときに読んでおいたほうがよい本です。
漢字学習をやり直してもいい

漢字を間違えたり、読めないと、少し頭が悪そうな感じになるよね?
某総理大臣とか(笑
人の教養の高さは語彙力で評価されることが多いのですが、漢字の読み方や意味を覚えるというアプローチで語彙力を伸ばすのもいいです。
漢字検定というメジャーな資格もあるので、成果の確認や目標設定がしやすいメリットがあります。
そういうのが好きな人はこのルートもありです。
それと、わからない言葉の意味をそのつど調べることも大切です。
自分が出会う言葉は、自分の興味関心、さらには人生に関わる世界のキーワードになっているかもしれないからです。
大人の漢字・言語学習といえば、出てきたときに調べるのが一番です。
現代文の基礎力アップに『田村のやさしく語る現代文』書評
「現代文というのは、筆者が書いた意見なら、内容がどうでもそれにもとづいて答えなけりゃならない科目なんだよ。」
引用元:『田村のやさしく語る現代文』 p.16
これは常識や善悪などは関係なく、問題文で作者の書いた文章から読み取れることのみを根拠として答えるのが現代文だ、という意味です。
もちろんテスト問題のことですが、こんな最初のほうに一般的次にこの『田村のやさしく語る現代文』で読解にはあまり知られていないであろう現代文というテスト科目の本質が書いてありました。

この著者の賢さは異常!
現代文というと何やらよく分からないものを直観的に答えるようなイメージを持っている人が多いかと思います。
ですが、実際には作者の文章だけが正しい意見であるかのような前提のもと、文脈や接続詞などから文章を解読していくのが現代文のテスト問題です。
現代文は問題を正しいルールで解釈して答えを出すという点で、他の知識を問う科目よりもむしろ数学に近い解き方をする科目なのです。
本書で現代文は数学と同じだと言っているわけではないですが、本書は始めにそのような本質を伝える構成になっていました。
とはいえ、現代文の入門書ではもっとも有名な部類に入る本書が、そのように説明してる訳ですから、今では他の本でも似たような説明をしているかもしれません。
誰が最初に分析したのかは分かりませんが、最初に大切な本質を説明してくれている点でこの作者に対する私の信頼性は一気に高まりました。

次元の違う名軍師の采配を目の当たりにしたような驚きだ!
受験現代文で多くの人たち進められている学習法がまずは『ことばはちからダ!』で語彙力を高め、次にこの『田村のやさしく語る現代文』で読解力をつけることです。
こちらもメインターゲットは大学受験生ですが、第一部の基礎力アップや第二部の実践問題も国語力アップに役立つのでおすすめです。
文章を厳密に解釈するスキルを高めるイメージです。
この本を読み、問題を解いて説明を理解していけば、言葉に対する分析力を高めることができます。
この本を読み終わる頃には、普段何気なく使っている言葉にこんな意味があったのかと改めて感心するように文章に対する見方が変わっているのではないかと思います。
それと同時に私が驚いたことは、私も含めて普段はそこまで言葉を厳密に使っていなかったことです。
簡単にいうと間違った言葉を気にせず使ってしまっていたことに気が付きました。
それとこちらは困ったことですが、多くの日本人が言葉を正しく使えていないことにも思い当たりました。
特に問題なのが、自分がどんなに正しく言葉を使っても相手が正しく理解しているかどうか分からないことです。
自分を棚に上げて相手の国語力を非難するつもりはありませんが、正しい説明をしてもあいまいに解釈されていることが多いはずです。
ですから、正しく説明しても理解されていない可能性が考えられます。
日本語は間違った表現でもそれなりに意味が伝わる反面、正しく理解するのは難解な言語になっています。
日本語を正しく理解している人はかなり賢くなれるのですが、そうでない人は賢くなるチャンスを逃してしまい知的な格差が生まれやすくなっているのではないかと考えられます。
今回は現代文の入門参考書から「言葉は理解されにくい」という驚くべき分析にたどり着きました。
頭のいい人以外には何を話しても半分くらいしか伝わっていないと考えておいたほうがいいだろうと思います。
さて、本書で出題されている問題についても少し書いておきます。
私が歳をとっているせいか、間違える度に著者田村さんの解説に対して異論を唱えたくなりました。
(補足 問題に間違えても自分の答えのほうが正しいと思うようになったということ)
例えば「必要なことは何か」などと広い意味でとらえられる質問には、つい自分の意見や価値観で答えたくなりました。
本当は私の解答のほうが正しいのではないかと感じました。

答えを疑うなんて少し傲慢な態度だわね
心理学的には相手から言われたことが理解できないときに、相手が間違っていると解釈したくなるという認知バイアスがあるので、その影響だろうと思います。
ですから、受験生のみなさんも現代文に限っては自分の解答のほうが正しいと思ったことのある人もいるのではないかと思います。
ちなみに、私の正解率は序盤のほうは9割方正解、中盤は8割、最後は6割くらいというところでした。
たぶん田村さんが意図的にそういう難度に設定したのだろうと思いますが、なかなか心憎い演出です。
この『田村のやさしく語る現代文』は説明や構成のレベルが高く、まさに名参考書というにふさわしいものでした。
もしもこの本に高校生のときに出会っていれば私の人生も少しは違っていたかもしれないと思わせる一冊でした。
また後で読み直そうと思います。
[おまけ] 現代文学習のポイント 説明力とスピードと経験
今回参考書を調べたついでに学習方法も分かりました。
受験生のみなさんのために現代文の得点力を高めるポイントを説明しておきます。
単に正解を選ぶ能力だけでなく、正解・不正解に対して、なぜ・どこが・どうしてなどと正しく解釈して説明する能力を高めておくことが大切です。
正しさだけでなく、間違いの理由もちゃんと客観的に説明できるレベルになれば、ある程度の実力が着いていると言えます。
次は、問題を解くスピードが速くなれば、現代文はほぼ攻略できたといえます。
後は狙った学校や資格などの過去問をたくさん解いて、パターンに慣れることで攻略してしまえば勝利は目前です。

それはその通りだろうけど、もっと早く知りたかったな……
[コラム] 現代文が作り出す忖度官僚
先に説明しましたが、大学受験の現代文は、あくまで問題文にある内容にそったものが答えとなる仕組みになっています。(設問からしてそうなっている)
現代文では文章や問題の作者の考えが正しいものであり、解答者となる学生の主張や価値観で答えてはいけないようになっています。
(補足 問題文にちゃんと作者の意見や文章の空欄などと書いてあるので、当たり前のことですが)
小論文という形で一応は解答者の意見に答える問題もありますが、全体に占める割合は小さくおまけのような扱いであることが多いです。
このような現代文で、高得点を取り高級官僚などになっていく人たちは、自分の意見よりも相手の意見をくみ取るのが上手な人たちに自然に絞られていくはずです。
その結果、行政の是非が問われる場面に出くわしても、何も言わずに上司の意向を忖度する忖度公務員が大量に生まれたということではないかと思います。
あるいは日本の教育制度自体が、自己主張をしない人を優遇する制度を目指しているということかもしれません。
自分の意見を言わないわけですから、自由な主権を持った人間とは言い難いです。
日本人はこのようにして自己主張せず主権も持たない国民性が形作られてきたのではないでしょうか。

行間というより空気を読んで忖度するのが公務員が生き残るコツだ!
Next Step 人の能力は話す力で判断される
国語力を上げるだけでも頭はよくなります。さらに基礎さえ身に着いてしまえば考えるたびに頭はよくなっていくでしょう。
ですが、人から頭がいいとかデキると評価されるには話す力も必要です。
人は話す力とさらにそのときの態度や見た目などで相手を評価するからです。
話し方ではわかりやすさや相手の言いたいことを正確に読み取る力が大切になります。
細かいノウハウは鉄板の話し方本があるので次を参考にしてください。
とりあえずこれを覚えるまで読み返しておけば口下手と言われることはなくなるでしょう。
むしろ、相手からは賢い人だと思われているはずです。
『「話し方のベストセラー100冊」のポイントを1冊にまとめてみた。』
姉妹本の文章術のベストセラー本もおすすめです。
SNS やブログ、ビジネスメールなどで良い文章を書いて周りの人と差を付けたい人はチェックしてみてください。
逆に相手の文章力を判断できるようにもなるので便利です。
こちらも鉄板本です。
『「文章術のベストセラー100冊」のポイントを1冊にまとめてみた。』
受験や資格試験をターゲットにしているのですが、鉄板の学習法が学べる本もあります。
基本は同じなので上位にランクインされているものは誰にでも役立つはずです。この本では記憶術に力を入れています。
ですが、本当は本質を理解してより少ない抽象的な原理原則から個別のことを判断して対処していく、演繹的な力を付けたほうがより賢い人になれます。
それと同時に個別の具体例から自分の理解している原理原則を修正していく帰納法的な思考もできれば完璧です。
『「勉強法のベストセラー100冊」のポイントを1冊にまとめてみた。』
試しに1冊ずつ読むなら
頭をよくするために今回紹介した本を、試しに読んでみるなら次の順がおすすめです。
- 田村の現代文
- 話し方100冊
- ことばは力だ
- 文章術100冊
- 勉強法100冊
本当は言葉を知ってから理論を学んだほうがいいのですが、1冊ずつ試すなら田村の現代文が国語の基礎力アップにおすすめです。
100冊系は本当は、[勉強法 → 文章術 → 話し方]の順で読んだほうが効率がいいです。
とはいえ、実際に日頃使えるのは話し方のノウハウです。文章を書かない人はいても会話をしない人は少ないです。
文章術もいいのですが、日頃よく使うであろう SNS のやり取りは会話に近いのです。
ですので、会話術のほうが役立つことが多いです。そもそも人が話し方で評価されることも忘れてはいけません。
この記事は単に頭を良くしたい大人の人の他に、出来れば頭がいい人だと思われたい人も読んでいるでしょうから会話術は役に立つはずです。
勉強法も先に学んだほうが全体の学習効率が上がります。受験や資格試験の勉強中の人にはかなりおすすめです。
ですが、各国語力(読解力/文章力/会話力)を高める補助的なスキルなので5冊全部読む予定がないなら後回しでいいです。
言葉も基本は理解しておきたいところです。とはいえ、知らない言葉や違和感を感じたときに検索すれば語彙力を高められるので3位にしています。
全部読んでみるなら
最後に今回紹介した本を全部読むなら次の順がおすすめです。
- 勉強法100冊
- ことばは力だ
- 田村の現代文
- 文章術100冊
- 話し方100冊
ベストセラー本はノウハウ辞典としても使えるので機会があるたびに読み返すと記憶に定着するのでおすすめです。
今回紹介した本
効率的な勉強法:戦う前に勝負はついていた
頭が良くなってきたら、資格試験のひとつも受けたくなるのが人情でしょう。
資格試験や受験勉強で勝つ方法は、いかに効率的に学習できるかで決まります。
現状・目的・方法を具体的に正しく理解し、それぞれに合った効果的な学習をするのが理想です。
その具体策を、「好き」と「嫌い」、「得意」と「不得意」の2軸のマトリクスに分けて説明したのがチームドラゴン桜の「なぜか結果を出す人が勉強以前にやっていること」という本で説明されています。
好きで得意なことはそのまま続ければいいのですが、不得意なことはやり始めるのも一苦労なので、習慣化やリマインダーで始めるきっかけを作る、嫌いだけど得意なことは時短を目指すのが効率的だなとといったノウハウが紹介されています。
“勉強は合理性と効率性を相乗した科学的トレーニングだ”とも説明されています。
いい表現です。たしかに論理的な世界なので合理性は重要です。

いやいや、結局、生まれつきの地頭が物をいう世界なんじゃないの?
学校で予習復習とかしなくても、できる子はちゃんとできてて、テストでも良い点をとってたよ。
そういう人もいるので、それもひとつの事実といえます。ですが、この本では地頭をよくする方法も説明されています。
基本的には、思考停止せずに疑問をもって本質を理解することを続けることをすすめています。
私の理解とほぼ同じですが、マンガを引用したり、具体例を出して、もっとわかりやすく説明されています。
この本はタイトルの「なぜか結果を出す人が勉強以前にやっていること」だけでも、キャッチーで興味を引きます。
内容もタイトルから受ける期待を裏切らない的確なものでした。
タイトルが気になった人には、大きな学びがあるでしょうから、目を通してみてください。
私が読んだときは980円の Kindle Unlimited の読み放題に入っていたので、ラインナップされている期間なら、こちらがおすすめです。
⇒ 【PR】Kindle Unlimited ガイド
オーディオブックが最も学びが多い!?
この記事では頭を良くしたい人はいったん大学受験の基本的な参考書を理解してみることをおすすめしています。
おすすめは『ことばはちからダ!』や『田村のやさしく語る現代文』です。
このレベルの基本を確認して、相手の言葉のひとつひとつを厳密に理解できるようになったら、Audibleなどのオーディオブックが学びが多いことがわかりました。
耳で聞くだけで読むストレスがなくて楽です。倍速再生で読むよりも早く知識を増やすことができるメリットがあります。
気になるジャンルの本を何冊も聴くのに向いていて、多角的に分析できて学びが多いです。
私ももっと早く試せばよかったと後悔したのですが、学習時間を楽に増やせるのが最大のメリットといえます ⇒ 【PR】Audible
おすすめジャンル
- 純粋に頭を良くしたい
⇒ ロジカルシンキング/学習法/脳科学/心理学/潜在意識 - 頭が良い人だと思われたい
⇒ 話し方の本/ロジカルシンキング - 仕事のために頭をよくしたい
⇒ 人間関係/営業などのビジネス本 - 家族や友人との人間関係をよくしたい
⇒ 人間関係/悩み解決/共感能力 - 出世したい
⇒ 人望を得る/マネージメント/マーケティング - 人生が辛いので楽になりたい
⇒ 不安/メンタル/心理学/脳科学/潜在意識
おすすめジャンルはいろいろありますが、学習効果や目的達成を考えると、潜在意識を理解して良い状態に変えつつ行動を続けていくのが一番おすすめです。
おすすめの著者
- 中野信子
- 野口悠紀雄
- DaiGo
- 水野敬也
私が Audible の聴き放題タイトルで聴いてみて学びの多かった著作者を紹介します。
中野さんはテレビにも出ているので浅いかなと思いましたが、とてもストレートに本質を伝える優れた学者さんでした。
本質を突いた脳科学系の話がおすすめです。本質を突きすぎていてることがあるのでメンタルの弱い人は慎重に聴いたほうがいいでしょう。
野口さんは元大蔵官僚の経済学者で経済や学習法などに優れた著作が多いです。少し難しかったり、独自の内容も多い気がしますが、本質を突いていて学びが多いです。
DaiGoさんはメンタリストとしてYouTubeやテレビなどでも有名ですが、普通に役立つ心理知識を披露しています。
日常的なテーマが多いので、カジュアルに心理や脳科学の知識をえるのにちょうどいいです。
真理を探求する学者ではなく、大衆向けにエンタメに寄せ内容で、心理研究とビジネスを両立させたスタイルのようです。
そのため、内容がやや浅めなので、気になることは他の人の著作で理解を深めていったほうがいいです。
それでも知識や情報として面白いテーマを扱っているので、カジュアルに聴くにはおすすめです。
他にはテレビに出ているような有名な批評家もいますが、テレビ系は雑談のような浅い内容のものが多いようです。
エンタメとしてはいいのでしょうが、学びを優先するなら浅いと感じたら聴くのを止めて次のタイトルを探した方がいいでしょう。
水野さんは『夢をかなえるゾウ』シリーズを大ヒットさせた売れっ子作家さんです。
『夢をかなえるゾウ』はビジネス系のコーチング本のような内容です。
ストーリーが良くできていて、ナレーションの読み上げスキルが高く、楽しめるシリーズになっています。
他の著作はまだ聞けていないので順位が低くなっていますが、『夢をかなえるゾウ』は私が Audible の読み放題で聴いたなかでは一番面白かったのでおすすめです。
【PR】Audible原理原則体系を磨く[理想論]
物事の本質を見極め、それを表す抽象的な原理原則をよりよいものに磨き上げていけば、さらに賢くなっていけます。
そのためにはルールや関係性などのインデックスをまとめた原理原則の体系を、自分の頭の中に作り上げていく思考実験を続けていく必要があります。
自分や他人の経験からえた具体的な知識ではなく、それを抽象化した状態で理解し頭の中の理論体系をよりよいものにしていくのがポイントです。
そうすれば抽象度の高いより上位の原理原則を元に適切な判断が下せる賢い人に近付いていけます。

本質というと難しそうだが、日頃からより上位の根本的な原理原則までさかのぼって、物事を判断するようにしておけば、自然とそうなるはずだ。

あの人にこう言われたと思うんじゃなくて、同僚の20代の女性にこういう価値観の元、こういう仕事のアドバイスをされたって感じに考えればいいだけよ。
分類能力といってもいいわね。

まずは簡単に思考停止しないことだな。
言ってることの根拠になる価値観や目的を原理原則レベルで理解して頭の中に整理していくんだ。

上位の原理原則をたどっていくと、それ以上さかのぼれなくなるんだけど、毎回そこまで考えるようにしてみて。
考え方はこれでいいのですが、自力で原理原則を考えるのは効率が悪いです。
人類が磨いてきた偉大な原理原則は、すでに良書に書かれているので、本を読んだ方がよりよいものが早く身に着きます。
もっと賢くなりたい人には読書が強力な武器になります。
凡人でも読書から原理原則を磨いていけば、いつかは読書をしない我流の賢者よりも賢くなれるはずです。
真の賢者や天才とは [自説]
前提としては、本質を読み解く能力と知識の多さが賢者や天才の条件だと考えています。
どうしたらそうなれるかというと、ビジネス書でノウハウをため込むよりも、小説をたくさん読んで本質を見抜く力を高めることが効果的です。
そのほうが賢者や天才に近づきやすいです。
もちろん高い国語力で言葉のひとつひとつを正しく理解し、状況を分析し、予想することを続けるような、正しい読書を続けないといけません。
この説は私の経験則にすぎませんが、東大や京大の知識詰め込み型のデータバンクタイプの人よりも、小説をたしなみ本質を見抜くタイプの人のほうが、頭の良さのレベルが高いように感じます。
これはいわゆる秀才と天才の違いです。
賢者や天才を目指す人は面白い物語に多く触れ分析力を高めてみてはいかがでしょうか。
国語力以外で頭をよくする方法
- 早寝早起き:記憶は睡眠で定着するので睡眠不足はNG
- 適度な運動:運動が認知能力が高まることが実験で明らかになっている
- 新しいことにチャレンジ:新しい経験の刺激が脳を活性化
- 頭のいい人と関わる:自分の力を試しつつ人から学ぶ
- 人とのコミュニケーション:実践で頭の良さを鍛える
本質的には洞察力と論理的思考力を高めるべきですが、認知能力自体を高めたり、賢い人から学ぶのも効果的です。
自分が求める頭の良さが何なのか、よく考えて望む頭の良さが手に入るように頑張って行きましょう。
よくある質問・疑問
大人が読解力を身に着ける方法は?
これこそまさに国語力を高めれば実現できます。受験の参考書だなどと馬鹿にせずに、この記事で紹介している『田村のやさしく語る現代文』などを読んでみて下さい。
本質的には内容を要約し本質を見抜く力をつけるのがおすすめです。
語彙力を高めたり、アウトプットすることも大切なので、会話やSNSなどで積極的にアウトプットしていってください。
大人に求められる国語力とは?
相手の話を理解し、自分の考えを伝えることが基本です。より論理的かつ効率的に、さらに短い言葉で理解し伝えられるとなおよいです。
今後の日本の若者に求められる国語力とは?
検索エンジンやチャットAIなどで手軽に答えが得られる現代社会では、正しさの先にある相手の意図を読み取ったり、自分の意図を的確に伝えたりする能力が重視されるようになるでしょう。
IT時代が到来する以前よりも、より本質的な理解力や心づかいが求められる時代になっていくはずです。
国語の読解力を上げる方法は? 読解力をつける方法
この記事で説明しているように、大学受験や高校レベルの参考書で語彙力と合わせて読解力を高めるのがおすすめです。
ひとつひとつの言葉の意味をより厳密に理解する力を鍛えていくことが大切です。
「人は失敗したときしか学ばない」という人がいますが、たしかに小説などを読んでいるだけでは学びは少ないです。
そこで成長するための失敗にちょうどよいのが国語の参考書だというわけです。
間違いを正していくことや、よりよい考え方を学ぶことが大切です。
読解力をより高めるには、ノートに要約を書いて、自分で客観的に分析すると効果的です。
作者の意見や自分の意見も客観的に分析することで新たな気付きが生まれ、それが学びとなります。
なぜ国語力が低下しているのか?
社会レベルでは、ネットの普及で情報伝達が文語から口語へ変わりつつあり、読書量が減っていることが原因だと分析されています。
欧米では自分の意見を正しく伝えることが美徳とされていますが、日本では自分の意見を持たず言わないことが良いことかのような風潮があるのも問題です。
そもそも日本は自分の頭で考え相手に伝える能力が育ちにくい社会になっているのもよくありません。
証拠や論理よりも誰が言っているかという権威性でしか正しさを判断できない人が多いです。
読解力が高い人の特徴は?
不明な点を的確に確認して誤解をなくすことで、正確に理解し的確な判断が下せることが読解力が高い人の特徴です。
ひとつひとつの意味を正確に読み取り、その意図通りに理解してから、適切に判断するよう心掛けていれば読解力を高めていくことができます。
国語に必要な力とは?
まずは読解力が必要です。そのためには語彙力と文法などのルールの理解が必要です。
それらで正しく理解する力を身に付けたら、次は文章や言葉で理解したことや筆者の考えを伝える能力が必要です。
最後に理解力や分析力を生かして、よりよい自分の意見を持ち伝える力を持つことが必要です。
国語という言葉の定義によりますが、学習レベルでは、まずは理解力が重要です。一般社会レベルではコミュニケーション力を高めることが重要です。
国語を勉強する必要性は?
母国語は理解や思考の基盤であり、言語の理解や技術は人生全体に関わる重要な能力です。
人は国語力がないと、自分の気持ちさえもうまく理解できません。
また相手を理解するコミュニケーション力の基盤でもあり、社会における人物の価値を決める基準のひとつにもなっています。
人が有能かどうかを判断する基準も、多くの場合、会話を適切に受け答えする能力で計られることが多いです。
このようにビジネスでも生活でも全体に大きく影響するのが国語力です。国語とはまさに最優先で勉強すべき学問であり技術であると言えます。
国語力がないとどうなる?
国語力がないと文章の読み書きを正しくすることができません。また、相手の考えも自分の考えも正しく理解することができず、誤解やトラブルを起こしやすくなります。
国語力のない人の人生は、たとえ裕福な家に生まれたとしてもそれを維持・発展させることができず、誤解や不満を抱えたまま、単純労働を繰り返すような厳しいものになってしまうでしょう。
国語力はコミュニケーションや人生の基盤となる自分の能力の基本なので、しっかり高めておくべきです。
今までの人生で国語力を高める努力をしてこなかった人は、おそらく今現在、満足した人生を送ることができていないはずです。
せっかくこの記事に出会ったのですから、この機会に国語力を高めて自分の人生を少しでも納得できるものに変えていってみてはどうでしょうか?
国語は将来的になんの役に立つ?
人とのコミュニケーションが的確にできるようになり、現在から未来まで仕事や人間関係の質を高めることに役立ちます。
また自分の気持ちや置かれた状況を客観的に理解するのにも役立ちます。
国語力がないと自分が言っていることや考えていることの意味すら正しく理解できず、不満を抱えた人生になってしまいます。
特に自分の頭で考えることを止めてしまうと、そこで人間的な成長も止まってしまうので、より正しく考え続けることが大切です。
国語は何を学ぶべき教科ですか?
学校教育においては、実質的には語彙力と読解力が求められるので、この二つを学ぶべきです。
具体的には、文章の作者や質問の文章をより正確に理解し、適切な答えを出す能力が求められます。
一般社会においては、この二つに加えて思考力やコミュニケーションスキルも求められますので、行く行くはこの二つも学んでいくべきです。
独学はムリ、教わりたい人向け
賢者とか天才を目指してる訳でもないし、「ダイエットは明日から!」という気ままなタイプの人にはライザップ理論でコーチに管理してもらえる家庭教師スタイルが向いています。
大人がサクッと現代文だけ教わる方法を調べたら、オンライン学習の中高生向けのコースがありました。
オンライン塾はどこもけっこうなお値段なのですが、お金があるなら個人指導などで学ぶのが手っ取り早いです。
サイトに中高生向けと書いてあるので大人でも使えるのか確認してみましたが、下にリンクを挙げてあるオンライン家庭教師は大人も指導しているので大丈夫とのことでした。
学習に使うお金は自分への投資なのでお金に余裕があるなら時間を節約できる分、結果的に得になる人もいるはずです。
本で学ぶ場合は、書いてある解釈で自分が納得するしかないというデメリットがあります。ネットで調べても本の中も問題や答えの解釈まではほとんど書いてないです。
それが質問できる人がいるなら自分の疑問に直接答えてもらえるので効率的です。
それと人が相手だと学習から逃げにくくなるのでモチベーションを維持しやすいです。
もっと手軽にオンライン学習
賢い大人を目指すなら高校レベルの国語力を高めるのがおすすめです。
とりあえずは本で独学すればいいでしょう。
ですが、一人だと続かない人には月2千円くらいのオンライン学習もおすすめです。
スタサプというのが授業とテキストがあって安い割には本格的な感じです。(ガッツリ学べる高額コースあり)
無料期間でお試しができて社会人でも使えます。
意外とハマって成績が伸びてきたら、少し偏差値の高い大学に社会人入学するような夢も広がります。
偏差値コンプレックスのある人がチャレンジしてみれば、ワンランク上の満足感の高い人生が待っているかもしれません。
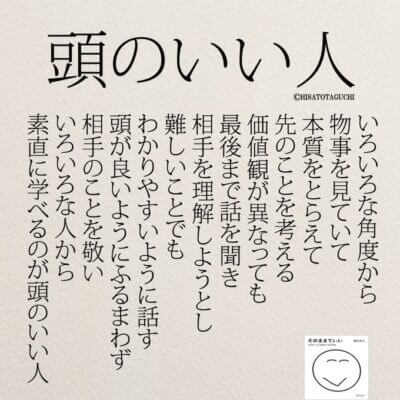







コメント